
田舎塾 報告とまとめ
八鹿病院は、地域の安全安心の象徴・拠点であり市役所と共に養父市で最も大きな経済流通高を誇る組織です。市民や但馬に住む多くの住民がなるほどその通りと思えるようにせねばなりません。 往復はがきの返信率は30%なんですが、いつも万難を排して参加してくれる友人も多く、それが継続の励みになっています。 今回は細川管理者による、医療・病院の現状解説と但馬の医療健康福祉的
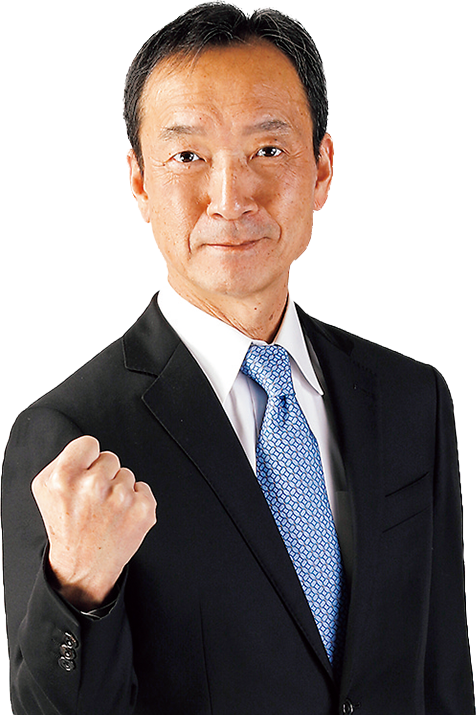

八鹿病院は、地域の安全安心の象徴・拠点であり市役所と共に養父市で最も大きな経済流通高を誇る組織です。市民や但馬に住む多くの住民がなるほどその通りと思えるようにせねばなりません。 往復はがきの返信率は30%なんですが、いつも万難を排して参加してくれる友人も多く、それが継続の励みになっています。 今回は細川管理者による、医療・病院の現状解説と但馬の医療健康福祉的

日時:平成25年5月31日(金) 19:00~ 21:00 場所:但馬長寿の郷 視聴覚室 講師:公立八鹿病院管理者 細川裕平氏 (前兵庫県但馬長寿の郷長、兵庫県理事・へき地医療支援担当) テーマ「僻地医療の課題と展望 ~八鹿病院の将来像~」

確かな未来を拓く「あしたのふるさと但馬」づくりへの挑戦 講師は石井但馬県民局長でした。兵庫県立美術館時代の経験談からスタートし、但馬の可能性について、持てるポテンシャルや、評価され出した但馬の話題についてお話頂きました。 前回の基礎的財政論から一転! 可能性の話しです。 さて次回から専門分野、教育・建築・農業・林業・市場経済・経営どれからスタートするか?
[gallery link="file" order="DESC"] 前回は基本的な財政状況について理解を深めて頂きました。今回はそんな厳しい中にあっても「但馬は捨てたもんじゃない!」こんな視点から但馬の特性や可能性について、但馬県民局長を講師に迎え意見交換を行います。。 但馬の課題と今後の展望、私達にできることを次第に明らかにして行きたいと思います。 記
田舎塾とは 将来への希望を見出しにくい経済状況からくる不安が政治行政への不信に繋がっています。税収が伸びない中、少子高齢化で医療・介護・年金など社会保障関係費が増大し続けることにより将来発展に向けた戦略的施策が打てなくなっているからです。解決方法は、まず現況を正しく知ること。次に対応策、解決策を見つけること。そしてそれぞれが自ら実行することです。 一人で悩む時間を、みんなで知恵を出し合い、協

~今更聞けない国・地方財政と運営~ 田舎塾への参加ありがとうございました。 細かい数値や専門用語は問題ではないのです。国と県や市の税財政の概要をシンプルに理解することが目的でした。 本庁財政課副課長 藤原俊平氏に資料を基に講演をいただきました。 政調会資料レベルでしたが、皆さん理解できたのでしょうか? ~これが解れば国会県会議員になれます~ 専門用語の解説や、疑問点は以降ずっとフォローしますの
