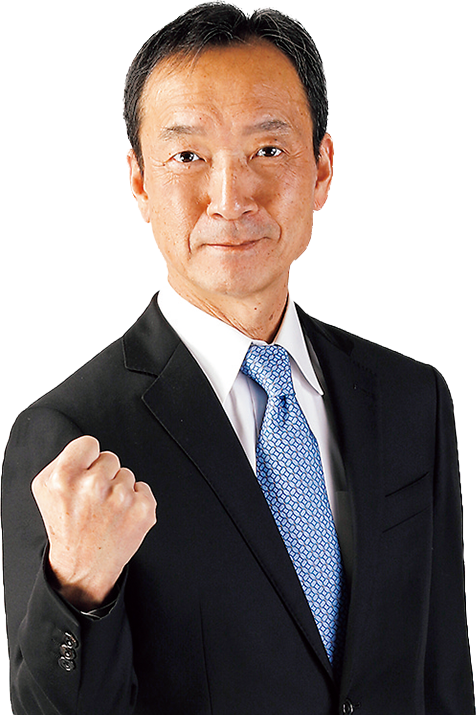みなみ但馬の3高校 後編

㈱第一学園高等学校養父校の創立15周年式典
養父市は旧関宮町、大谷小学校舎に当時の名称ウィザスナビ養父高等学校が開校しました。現在の第一学園高校の岡本校長先生は八鹿高校での勤務経験もあるとか、他にも地元の教員OBの方、地域歴史や美術を教えている方々など教師・事務員の多くは地元採用です。
15年で1300名以上の卒業生を送り出しているそうです。通信制でのオンライン授業は自宅・出先などでリアルに受けれれる他、録画受信も可能。スクーリングは週一?で登校し教員が授業相談また集団行動として農業体験、地域住民との交流、契約宿泊先などが用意されています。
全日制と違い、生徒の生活環境に会わせて単位取得をすることが出来ますが、課題は毎日登校し教室で仲間と学習するという習慣から外れることからは、自分の学習への元ベーションの維持できるかどうか?でしょうか?(私なら)。一方で学び直しや、将来の職業を選択済みで既に特定職業教育を受けているあるいは既に就業中の人にとっては有効な選択肢になります。
■
全日制は生徒指導がしやすい反面 時間と場所を決めて多人数が集まらねばならずコスト面では不利です。通信性高校の生徒数は近年据えていますが、教科の単位認定が甘く、実力を伴っていないとの指摘もあるところです。 全日制が汗が飛ぶ熱いライブなら通信制はCDで聴くようなものです。
~アナログとデジタル~
20日は県立八鹿高校の同窓会親睦総会
みなみ但馬の進学校でもある八鹿高等学校、文武両道で国公立大学への進学は40名超、部活においても特に音楽部、西洋画部などは県下・関西でも上位入賞することが多い。OB会も活発で毎年卒業期別に世話役を決めて親睦総会が開催されている。今回は渋谷校長による学校情勢報告、合唱部による歌の披露やOBで活躍中のオペラ歌手、中川さんのステージで盛り上がりました。今回も参加者は世話役を入れてほぼ300名弱、伝統校ゆえのまとまり感でしょうか? 学校は現在学年5クラス、もちろん全日制です。
今後の学校の在り方
一学年5クラスは他に豊岡高校、こちらは旧制中学の伝統と誇りでOB会も盛ん。
しかし全日制普通高校の規模からいえば6~10クラスには届かず多様な教師陣の確保、集団行動による体験と切磋琢磨出来る環境からはギリギリのラインにあります。また但馬での出生数がR3年900人であったことから計算すれば令和18年の高校入学者数は22クラス未満、北但で3校12クラス、南但で2校8クラスでしょうか? 統廃合による適正規模化だけでは多様な教育環境整備はできないことになります。 (適正規模という単純な効率性追求の限界) 遠隔授業の在り方、AI・IOTの更に有効な使い方の模索が求められます。学区内高等学校は競争の時代から共存共栄の時代へ
- 文科省指定校制度の中に遠隔授業配信の定員枠40を超える複数校での一括配信授業への取り組み
- 受信側の少人数習熟度別指導体制の整備、単位認定への受信校担任の積極的関与
- 地域拠点高校からの複数校教科担任制の導入と拡大
- 夏休み等を利用した集団体験学習や課外授業
- コミュニケーションや対話能力の体系的取り組み
これらは必要だと思うのは私だけでしょうか?