兵庫県議会議員みなみ但⾺選出 藤⽥ 孝夫(ふじた たかお) オフィシャルサイト
活動情報
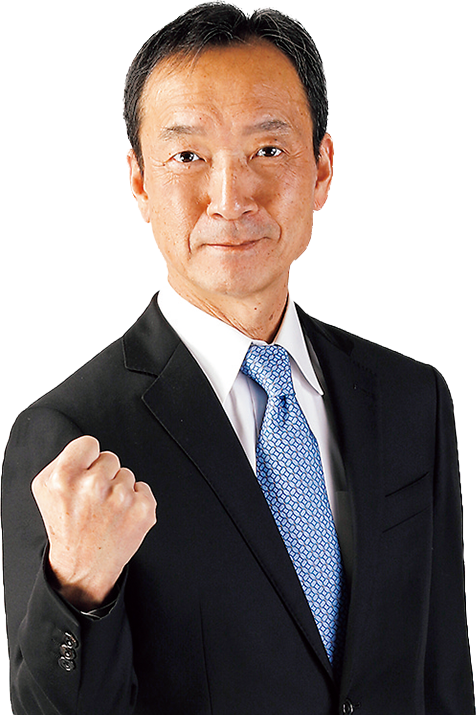

池田草庵が江戸時代に開いた漢学塾「青谿書院」は土地建物・遺品や資料などが県指定文化財となっています。
文化財と聞いて私達が即思い浮かべるのは国宝級の建物や、刀剣・絵画・陶芸品など形ある貴重品です。しかし青谿書院の建物や資料は、一目見てスゴイと思わせるものはありません。けれども多くの近現代史に名を残す活躍をした塾生を輩出したこと、池田草庵の教えの研究は今でも定期的に地域の有志で行われておりその解説本は学校教育にも活かされています。
「清貧にあまんじて生き方を探り、故郷で人材を育てる」というのが草庵先生の青谿書院の目的でした。養父市の学校では草庵先生の教えを「慎独」という象徴的な言葉として今も大切にしています。いつでも自分の内面の倫理観に基づき自分自身を律する という意味です。
さて現代社会、自家用車やテレビ、パソコン、スマホは一家に一台から個人に一台が所有するなど、赤貧・清貧とは真逆のモノが溢れ使い捨てるような時代です。PC(コストパフォーマンス)からTC(タイムパフォーマンス)が重視されています。当然メディアもテレビやラジオ、新聞などのメディアに加え、個人個人が投稿するSNSは圧倒的スピードと投稿数です。便利な情報もありますが個人的な好き嫌いや他者意見への反対、不快感を激しい言葉で表す投稿(公開叱責)や、漫才のネタみたいな仮想想定上のジョークは、特に政治・選挙ネタの閲覧数を稼げるようです。これら瞬時にイエスかノーかの判断を迫る投稿は、エックスやフェースブック、インスタグラムなどで共有拡散され、その閲覧数に応じた広告効果が期待されることから、閲覧数に応じた報酬を獲得できるアテンションエコノミーが成立しています。
私達の暮らしには多くモノが溢れ、必要な情報も必要ない情報も各自が好きな時に好きなものを閲覧でき、また自らも発信できる環境にあります。
しかしこんな時代だからこそ、今日明日の損得・様々なランキングに左右されることの無い。また物事を判断する上での価値基準たる自分自身の長期的な選択優先順位や内なる倫理観こそが必要です。
青谿書院と資料館、そして今回、トイレや事務所・研修室を備えた交流学習館が揃いました。
今まで以上により多くの方々に来場いただき、一見地味~な青谿書院が何故時代を創る人材を多く育成できたのか? 文化財たる所以を知って欲しいと思います。特に幼い頃より定期的に「慎独」を実践する場所として青谿書院交流学習館が多いに活用されることを期待します。
屏風絵の厳しい表情しか知らないけど、草庵先生もきっと喜んで下さると思います。
概要
種類別文化財の詳細
- 有形文化財(建造物)
- 国宝・重要文化財(建造物)
- 登録有形文化財(建造物)
- 有形文化財(美術工芸品)
- 無形文化財
- 民俗文化財
- 記念物
- 文化的景観
- 伝統的建造物群保存地区
活動報告最新記事10件
- 2025年12月03日
祝 朝来市制20周年 - 2025年11月29日
関西広域連合15周年 - 2025年10月15日
兵庫県立但馬農業高等学校創立50周年 - 2025年10月07日
お米について少し考える - 2025年08月26日
今夏の農業水不足対策 - 2025年08月04日
安全衛生大会・林業技能検定 - 2025年07月15日
青谿書院交流学習館 竣工 - 2025年07月01日
区長総会 - 2025年05月25日
県庁舎建替え3年間の空白 - 2025年04月28日
議案の態度
