現代官僚制×ボトムアップ
 1 県民ボトムアップ型県政について
1 県民ボトムアップ型県政について
■
(1)ワーケーション知事室の有効性について
■
長い歴史を持つ合理的な現代官僚制に属す県庁組織は権利・階層・専門性・文書主義で統制されています。規則万能 責任回避・自己保身 秘密主義 前例主義 権威主義 狭い縦割り等と多くの欠点を指摘され続け、時に事件となってもなお これに代わる新たな組織体制は存在していません。つまり最終決定を間違わないためのルールに則り、組織の上層に位置する人達に最終決定権を与えると同時に同等の責任を課す仕組みです。これを組織論ではトップダウンの仕組みと言います。
■
今定例会で知事が提案されている県政改革方針にも謳われている県民ボトムアップ型県政の具体的取組としてワーケーション知事室、学生未来会議などが行われました。12月議会で我が会派の松本祐一議員の質疑に対し知事は「創造性と自律性を持つ県民との開かれたパートナーシップを作るため現場主義を徹底し、ワーケーション知事室、学生未来会議など、県民の皆さんとの直接の対話の機会を拡充させ、県民により近いオープンな県政運営をしてまいりたい。県民の声をいかに聴くかということについては、これは、まさに県民ボトムアップ型県政の推進に当たっては、極めて大切な視点であるというふうに捉えており、コロナの状況も踏まえながら、具体的な取組を段階的に実施してまいりたい。」と、答弁されています。
■
12月に北播磨で行われたワーケーション知事室のように1泊2日、約60名の方と意見交換されたとして、仮に年10回開催で意見交換できた県民は約600人、542万人県民と意見交換するのであれば、1万年掛かかります。また今後もワーケーション知事室や学生未来会議が県内各地で開催されるのであれば、そうした場で聞かれた意見を県事業として取り挙げる優先順位はどうなるのでしょうか。また実現されなかった時、県民は落胆もするでしょう。知事のインフルエンサーとして地場産業のPRやビジネスマッチングの意味合いも含んでいるとはいえ、そもそもボトムアップ型の課題認識がその現場にあるのでしょうか。(災害被災地にはあると思います)
■
DXを推進している今、それでも人と会うことの意味は、自ら足を運んで、時間と場所を共有し齋藤知事の人柄、人となりを知ってもらうことで、齊藤県政理解の素地を作ることにこそあるのではないかと思えてなりません。県民ボトムアップ型県政を推進するにあたって、改めてワーケーション知事室を実施する目的を伺うとともに、スケジュールを含めた今後の進め方について伺います。
(2)DX化の推進について
■
県民の意見を聞くことから始まるボトムアップ県政、齋藤知事らしくスマートに正確に聞く方法が必要ではないかと思います。この際、曖昧な人の記憶や声の大きい少数意見は不要です。
一人の県民が感じている課題は、実は多くの県民が感じている共通の課題であったりもします。課題やアイデアをプラットフォームに投稿、第三者が共感する、また知ってる誰かがアイデアを出す、それを知事(担当課)が正式な回答をする。新県政推進室(企画県民部、県民生活課デジタル推進室)が担当し部局担当課へのトリアージュを行えばよいでしょう。
民主主義制度に詳しい議場の皆さんは既にお気づきでしょう。私は台湾政府のジョインをイメージしています。
アメリカ合衆国政府に対する請願を行うためのウェブサイト「WE the PEOPLE」は一方通行ですが、台湾政府IT大臣オードリー・タン主導で運用している「ジョイン」は、シニア層から選挙権を持たない学生若者まで幅広い年代の国民が、アイデアの提案や議論ができる双方向のコミュニケーションの場となっています。また、提案したアイデアが60日以内に5,000人の賛同を得られた場合、その提案に対して行政の関連部門は、2カ月以内に書面により回答することにもなっています。
例えば、プラスチックごみの海洋流出について、ある投稿者は、プラスチックスプーン、ビニール袋などの使い捨て製品の禁止を提案したところ5,000人以上の賛同が得られたため、台湾政府は、利害関係者と政府関係部門を招集、提案者を招待して協議しその会議内容を「ジョイン」で公開しました。そして最終的には段階的に対象を絞った方法でプラスチック規制を実施していくことになりました。
日本でも海洋生物のポリ袋等の誤飲に対して、魚の嫌う成分を含むポリ袋の製品化が目指されていますが、発案者は神奈川県の女子高生でした。
さて兵庫県で実施する場合、投稿できる分野は、県政改革、教育、スポーツ、健康、社会保障、環境・資源保護、交通など考えられますが、当然予算配分や事業優先度など県財政運営の方針に理解無きものは受け入れられません。また市町が実施主体となるものはどう処理すべきか検討が必要です。
県議会に於いても、決議、請願、国への意見書などは比較的ルール化しやすいように思われ今後検討しなければなりません。県民は、提案がいつ行われたのか、その提案に何人賛同者がいるのか、行政が提案に対してどのような回答をしているのかリアルタイムで把握できる。このように意思決定のプロセスの透明性が確保されていることが県民と県政の一体感、行政に対する信頼感につながると思われますが、県民ボトムアップ県政の進め方について何を目的にどんな手法で進めるのか、デジタルプラットフォームの開設も含めて知事の考えを伺います。
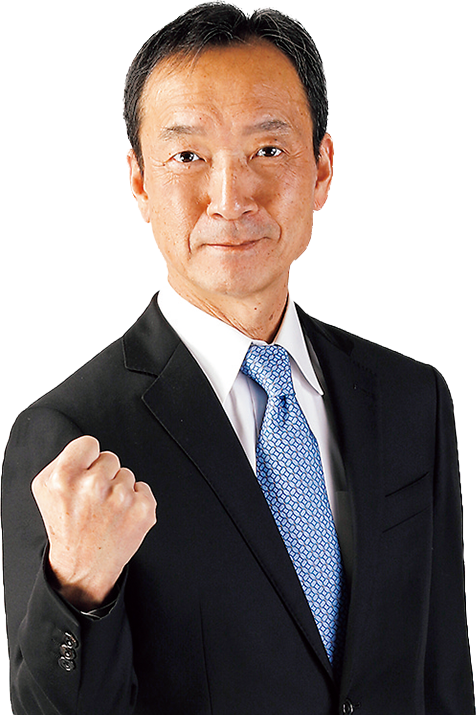
 1 県民ボトムアップ型県政について
1 県民ボトムアップ型県政について
