兵庫県議会議員みなみ但⾺選出 藤⽥ 孝夫(ふじた たかお) オフィシャルサイト
活動情報
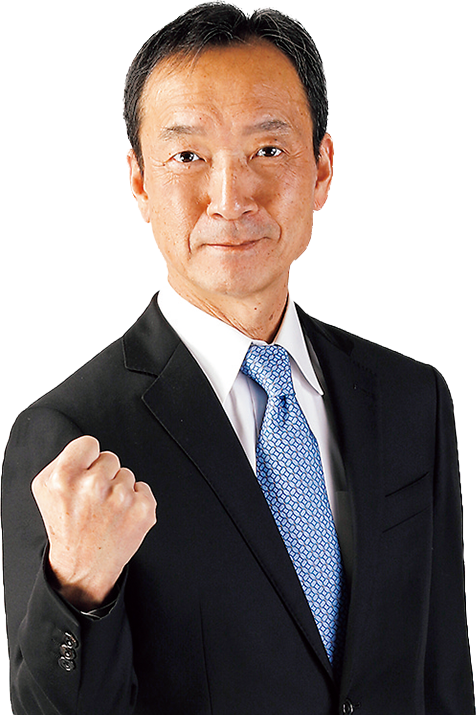

役職柄、いろんな学校に行かせていただくが、式典等では私なりのチェック項目がある。それは生徒や先生の挨拶、式典進行のスムーズさ、生徒の国歌斉唱・校歌斉唱の声の大きさや態度などです。これらを先生生徒が一定基準を目標とし多くの関係者が集まる祭典を作り上げることも教育の一部かもしれません。 但馬農高の本式典は生徒の質問や謝辞、大型パネル、エグザイルの講演など生徒の主体的な工夫が見られました。
*EXILE SHOKICHI氏は但馬農高産の但馬牛「みゆきひめはる号」を北海道の牧場で飼育中
もちろんそれだけのチェック項目で学校や生徒を評価すべきではなく、ご案内頂いたことに感謝しつつ祝意を述べることが今後の学校運営に活かされればうれしい限りです。(他人事ではなく県議として農業高校のポジションを考え提言せねばなりません)
農業高校とあって来賓は衆議院、県議、市議、市町、県民局長、農業振興事務所長や農業改良普及センター町、また近隣高等学校長、同窓会や歴代校長先生など約50名でした。
来賓祝辞は代表して谷衆議院議員の代読を秘書の方が述べられました。さて私の但馬農業高等学校の今まで果たして来られた役割と今後について・・・
■令和の米騒動で、お米だけでなく食料やエネルギーの生産と供給、そして価格と自給率など食の安全保障が大きな関心を集めました。そんな意味から第一次産業である農業・林業・畜産業・水産業の重要性を再認識しなければなりません。
■かつては農家を継ぐ男子生徒が多く通っていた農業高校ですが、50年で環境は激変しました。兼業農家の減少で農業人口は減少し続けています。一方で但馬牛、神戸ビーフ、朝倉山椒、岩津ねぎ、蛇紋岩米、但馬ピーマン等・・・世界的な日本食ブームもあって日本の農産品が高評価を得て多くの地域ブランドが誕生しています。日本の田舎を語る時、必ず地場品・特産品として地域イメージとなっています。
■今のように海外から豊富な食糧が入らず日本が国内産だけで食料を賄っていた時、それは江戸時代までです。当時の人口は3000万人、基本的に白米と魚、野菜、汁物が基本で今から考えると 栄養学的にも量的にも十分とは言えず、それゆえ日本人は体型が小さく、体力的にも欧米はじめ海外から大きく劣っていました。そして現在の食料自給率40%、狭い耕地面積を効率的に使う日本の慣行農法で農薬・肥料の使用過多も大きな課題となりました。
■国は緑の食料戦略を策定し2050年までに農薬を50%削減する、化学肥料を30%削減ことを目的に、有機農地の比率を25%までに拡大することが掲げられました。水稲では環境創造型農業などで少し先行している兵庫県も、人と大地にやさしい持続可能な農業の推進に取り組んでいます。
そんな大転換期にあり、但馬農業高校は日本の農業を机の上での勉学と農場など現場の両方から支える役割を50年間果たして来られました。
■但馬農業高校の校訓「汗をいとわず、命を尊び、日々高きを志す」は現代社会に欠落しかけている、しかし誰もが重要だと認識し始めた生きる姿勢や人生訓としての示唆に富んでいます。株価や通貨相場に一喜一憂する現代では人工的な評価基準でゲームのルールを学べば短期的に優秀な結果が得られるかもしれません。しかし長期的な人間関係や自然との関りを無くして社会では永続的な価値を生み出すことはできません。
■校訓を農業に例えると「春に種まき、夏に手入れをし、秋になって収穫する」つまり必要な努めをコツコツ果たし作業は行わなければならない、蒔いたものしか刈り取ることはできない、そこに近道はないということをあらわしています。
■人の成長や人間関係も自然界のシステムの一部であり生物と関わる農業の法則が支配しているのかもしれません。そのような意味において平均的必修である学校教育・教科はもちろん、但馬固有の地域資源でもある農畜産と加工、その歴史伝統を学び最新技術導入方法を学ぶ。同時に自然の摂理を体験しながら理解し農業と融合させていくことは高校教育の新たな分野でもあります。
■ 時流は先ほど申し上げたとように確実に変化し追い風が吹いています。但馬農業高等学校の50年間の歴史が地域の農業を維持し守ることをが評価されるとすれば、次の10年は農林畜産の大きな将来の目標を設定した挑戦であって欲しい思います。 食やエネルギーなど欠かすことの出来ない第一次産業が支える地方創生が具現化する中で、但馬農高の果たす役割は新価値観への挑戦の素地を創っていくことであって欲しいと思います。
活動報告最新記事10件
- 2025年12月03日
祝 朝来市制20周年 - 2025年11月29日
関西広域連合15周年 - 2025年10月15日
兵庫県立但馬農業高等学校創立50周年 - 2025年10月07日
お米について少し考える - 2025年08月26日
今夏の農業水不足対策 - 2025年08月04日
安全衛生大会・林業技能検定 - 2025年07月15日
青谿書院交流学習館 竣工 - 2025年07月01日
区長総会 - 2025年05月25日
県庁舎建替え3年間の空白 - 2025年04月28日
議案の態度
