
コウノトリ但馬空港20周年
先人達の夢をのせて一番機が飛んで来てから20年、県や市挙げての一大イベント夢但馬も20年ぶり。同時に空港のあり方考える利活用検討委員会も設置された。 コウノトリ但馬空港シンポジウムが開催されました。スピーカーは、日本航空会長の大西賢氏、豊岡市長中貝宗治氏、城崎は西村屋会長、西村肇氏です。日航会長の弁から、即東京直行便就航はなかったものの、伊丹~東京便のような大需要ビジネスニーズ以外のローカル
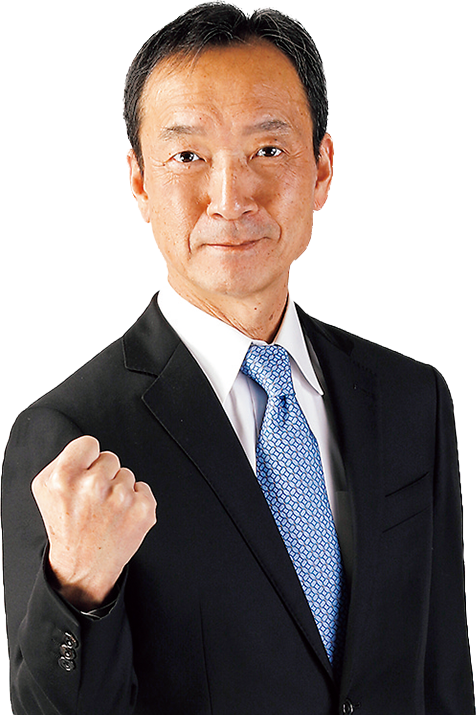

先人達の夢をのせて一番機が飛んで来てから20年、県や市挙げての一大イベント夢但馬も20年ぶり。同時に空港のあり方考える利活用検討委員会も設置された。 コウノトリ但馬空港シンポジウムが開催されました。スピーカーは、日本航空会長の大西賢氏、豊岡市長中貝宗治氏、城崎は西村屋会長、西村肇氏です。日航会長の弁から、即東京直行便就航はなかったものの、伊丹~東京便のような大需要ビジネスニーズ以外のローカル
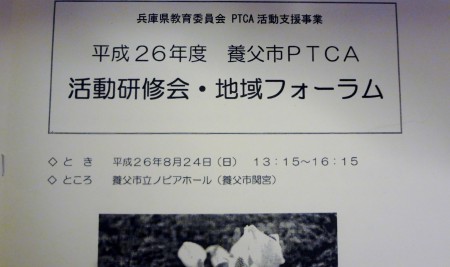
夏休みが終わる頃開催される、養父市PTCA実践発表会、本年は関宮のビアホールでした。 9歳で「天才児登録」され、14歳でカナダのトップ大学5校に奨学金付き合格を果たした大川 翔くんてみなさん知ってます?最高峰の大学が「ぜひ、わが校に!」と奨学金を上乗せして争奪戦を繰り広げており、その去就が注目されている気になる大学の進学先ですが、ブリティッシュコロンビア大学サイエンス学部に決

過日、兵庫県議会産業労働常任委員会が但馬を視察調査しました。地元選出議員として同行し地元事情等を説明するのも大切な役割です。監査の合間で私が時間融通できた日が豊岡鞄ストリート、アルチザンアベニュー等の調査日でした。実は私初訪問でした。 豊岡の地理的特徴と生物多様性、産業と結び付かせるストーリー展開は、ジッパーク、コウノトリ、柳行李=鞄と結び付きました。なんでも正倉院鳳凰堂に保存されて
本年度私は監査委員を仰せつかっています。議会三役と言われながらも今まで全く日の目を見ることなく影の存在監査委員。地方自治体の内部、つまり同僚が同僚を監視講評する監査委員会、(外部の有識者(藤川氏)も加わっています)その存在意義を少し触れてみます。 とはいっても、監査委員の守秘義務があるので個別具体の案件を例えに出すことは許されません。神戸県民センター、阪神南県民センターの監査からスタートして感じ

ビバホールチェロコンクールの究極の楽しみ方はなんといっても、出場者を支えることです。食事の世話、洗濯、朝の目覚まし、演奏を聴く、結果発表会に付き添など、それこそコンクールで上位を狙う彼ら(高校制や芸大生)を家族として受け入れることです。 彼らの成績はもちろんのこと演奏の自己評価を我が事のように共有することです。楽しみ方ではなく苦しみ方になる神経質な人は向きません。 もっともそれは女性(主婦

「地域づくりに協力したい」「出来れば地域外の人とも交流したい」「地域の資源をもっと知ってもらいたい」非常に良い市民意識です。市や県は公的資金で援助をする理由は、そんな気持ちへの福祉的配慮かもしれません。 では観光施策とは福祉施策と同じか? そんな訳はありません。 老人施設を建設するのと観光商品開発は全く別ものです。市や県の観光振興と民間(観光協会員)の役割分担を整理する必

鹿を獲るために設置した檻にクマが入りました、捕獲連絡している間にクマは鉄筋を押し広げ逃げてしまいました。それにしても生死を賭けた野生パワーの凄さには驚くばかりです。そこで緊急対策を講じることに・・・ 檻に「クマお断り」の看板を付けるとにしました。 大げさなタイトルですが、国県市の通常事業ではなくて但馬県民局で本年度行う独自施策や特徴的な事業が掲載されています。但馬県民局幹部と但馬の首長、県会

シルバー人材センターから戴いた天日干し棚田米のお茶漬けをかき込んできました。おかずは香住で加工されているサバのヘし子、かみさんが漬けたきゅうりの浅漬と母が炊いてくれた朝倉山椒とヤマブキの佃煮でした。 夏の我が家の定番昼ごはんです、そんなことはどうでもよいのですが・・・・・ 会場はずっと豊岡市民会館だった 金子組合長の狙いがあるのか? 農業特区に指定された養父市でJA但馬第19回通常総代会が開

蚕の里イベントが大屋で行われました。そこでタイムリーな資料を頂きました。『富岡製糸場と養父市の養蚕』(養父市教育委員会発行)です。イベントでは地域の物産紹介と若干の販売、ビックラボ(芸術村)のスチールパン演奏、それと画像の繭から糸を取り出す実演などでした。 さて養父市の養蚕歴史は、旧養父郡が明治以降の近代化にどんな役割を果たしたのかを教えてくれます。私の微かな記憶にある昭和3
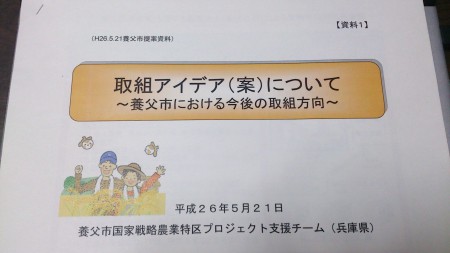
養父市の農業特区指定、兵庫県も応援しています。そのそも農業特区を国が指定する本来の目的とは何か? これは養父市固有の問題解決がひいては、全国的な農業問題の解決につながるとの仮説があるからに他ならない。 即ち養父市の提案はいずれ兵庫県や全国に波及できるスタンダードに成り得るものであることも求められている。 では日本農業の根本的問題は何か? それは中山間地の農業では専業でも暮らし

松の木の話題ではありません、水戸岡さんが手がけた豪華観光列車の名前です。オリエンタルエクスプレスみたいなものです。くろまつは今月下旬より北近畿タンゴ鉄道で運転開始され、当地原産の食材を使った料理も楽しめる車両です。 私たち(北近畿鉄道複線電化促進期成同盟会)はより高度化した鉄軌道整備を各会に求め、ひいてはそのことが地域発展に繋がると思っています。この思いは正しいのですが、通学生徒や高齢者など交通

前回は参入企業や流通業者ではなく農業生産者にとっての農業振興がテーマでしたが、加工流通など大規模にかかわる人材がいない中山間地にとってやはり重視すべきスタンスは生産です。今回はその続き 大屋高原有機野菜の初出荷式が本日行われました。近年は県議会公務と重なり出席できていませんでしたが、本年は2年ぶりかな?水芭蕉祭りに次いで高原に登りました。(いつも快晴です) さて、おおや高原
